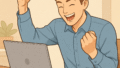引き継ぎは“全部やる”ことより、“何に力を入れるか”が大事だと気づいた話
こんにちは、キャリアコンサルタントのみってるです。
今回は「引き継ぎのあり方」について、実体験をもとにお話しします。
・新しい上司の引き継ぎが1日だけだったことにびっくり
・営業時代の自分も、実は事務作業の引き継ぎはしてなかった
・限られた時間とエネルギーの中で「何に力を入れるか」が大事
・仕事の中でやらないことを決めるのも、働き方の工夫になる
というお話です。
それでは、本文へどうぞ。
引き継ぎはどこまで必要?限られた時間と力の使い方
こんにちは、キャリアコンサルタントのみってるです。
今日は「引き継ぎ」について改めて考えるきっかけがあったので、少しお話しします。
新しい上司の引き継ぎは、まさかの1日だけ!
今日、職場に新しく着任した上司とお話する機会がありました。その中で、「引き継ぎが1日しかなかった」と聞いて、とても驚きました。
1日だけ!?と思った方も多いと思います。実は私自身も前の仕事では、引き継ぎに約2週間かけていたので、余計にびっくりしたんです。
でも振り返ってみると、私の引き継ぎも「全部」をやっていたわけではありませんでした。
営業の引き継ぎは丁寧だったけど、事務はほぼスルーだった
当時は営業職でしたから、引き継ぎはお客さんへのあいさつ回りがメインでした。アポイントを取って一緒に訪問し、「担当が変わります」と紹介する。これが2週間かかった理由です。
でも内勤の業務、たとえば事務作業や資料作成のことになると…ほとんど何も引き継いでいなかったのが実際のところです。
というのも、社内で使う資料やフォーマットはすでに決まっていて、「この通りにやってください」という感じでした。自分なりに作った資料や表もあったけど、それは自分の判断材料に使うだけ。だから人に渡す必要もなかったんですよね。
営業は営業、事務は事務。どこに力を入れるか?
営業部門にとって一番大事なのは、お客さんとの関係づくりや提案活動。事務仕事はもちろん大切ですが、優先順位で言えば営業活動のほうが上です。
それを考えると、私の引き継ぎも「本業」に重きを置いていたのだと思います。そして今日話した上司の引き継ぎが1日だけだったのも、そういう“力の入れどころ”をしっかり割り切っていたからなのかもしれません。
もちろん、1日で全部わかるわけじゃないです。実際にやってみてから分かることの方が多いですし、そこから学ぶことの方が多い。だからこそ「全部教えます!」よりも「まずやってみる」が大事な場面もありますよね。
「やらないことを決める」のも大切な仕事のスキル
今回、改めて感じたのは「人間の時間とエネルギーには限りがある」ということ。全部をやろうとせずに、「どこに力を入れるか」を自分で決めていく必要があるということです。
つまり「やること」だけじゃなく、「やらないこと」もはっきりさせておくのが大事。これができると、仕事の中で無駄なエネルギーを使わずにすみます。
昔は「何でもやらなきゃ」と思ってましたが、最近は「やるべきことに集中する」ほうが成果につながると実感しています。
僕自身のこれからの働き方にもつなげていきたい
この引き継ぎの話から、私自身も今後の仕事の進め方を見直そうと思いました。
やるべきことに集中する。
そして、やらないことは最初から「やらない」と決めておく。
そうすることで、心にも余裕ができて、仕事に対して前向きに向き合える気がしています。
「何でもやろう」じゃなくて、「やることを選ぶ」。
この考え方、これからも大事にしていきたいです。
【まとめ】全部を引き継がなくてもいい。大事なのは“どこに力を入れるか”
今回は「引き継ぎってどこまで必要なんだろう?」というテーマで、自分の過去と新しい上司のエピソードを重ねながら考えてみました。
● 引き継ぎは“全部やること”ではなく“大事な部分をどう渡すか”がポイント
● 限られた時間とエネルギーの中で「どこに力を入れるか」を決めることが必要
● やることより、「やらないことを決める」ことの方が意外と大事なこともある
● 自分にとっての“優先順位”を意識して仕事に取り組むことで、よりスムーズに進む
新しい職場でも、今の仕事でも、「まずやってみて覚える」という考え方はやっぱり強いです。
それでも、少し立ち止まって「この仕事、本当に今やるべき?」と考える時間があると、もっと楽になるかもしれません。
このブログが、誰かの働き方をちょっと楽にするヒントになればうれしいです。
それでは、また次回のブログでお会いしましょう!